アドラー心理学における自己決定性は、自分の人生の選択を主体的に行う力のこと。
この自己決定性を活用することで、職場では主体的な行動や課題解決能力の向上が期待できます。
具体的には、指示待ちではなく、状況を判断して自ら行動する、失敗から学び再挑戦する、といった姿勢を促すことができます。
本記事では、いくつか想定できることを考えながら、アドラー心理学の自己決定性を上手に活用する方法をまとめてみたいと思います。
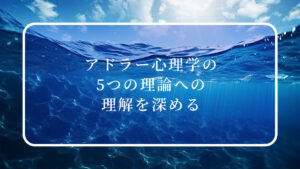
自己決定性とは何か
アドラー心理学では、人は環境や過去の出来事によって完全に決まるのではなく、自分の意思で行動や選択を決められると考えます。
自己決定性は「周囲に流されず、自分の目的や価値観に基づいて決断する力」とも言い換えられます。
ただこの考え方は、単に「我を通す」こととは異なります。
本来の自己決定性は、状況を正しく把握し、自分の責任の範囲で最も適切だと思う選択を行う能力を指します。
外部の条件や他人の意見を考慮しつつも、最終的な判断を自ら下すことが重要です。
日常や職場での活用例
1. 職場での主体的行動
例えば、会議中に議題が脱線し、結論が出そうにない状況があります。
自己決定性を持つ人は、司会者に任せきりにせず、「この部分を整理して提案してもよいですか?」と提案し、方向性を戻す行動を取ります。
これは単なる「お節介」ではなく、組織の目的達成に向けた主体的な働きかけです。
2. 私生活での意思決定
休日の予定を立てるとき、「友人が決めてくれるまで待つ」のではなく、自分がやりたいことや行きたい場所を提案します。
この小さな行動も、自己決定性を鍛えるきっかけになります。
3. 失敗からの再挑戦
プロジェクトでミスをした場合、上司や同僚に責任を押し付けるのではなく、「自分の選択の結果」として受け止め、原因分析と改善策を考えます。
そのうえで再挑戦する姿勢が、信頼と成長の両方につながります。
自己決定性を発揮するためのポイント
自己決定性は「強い意志」だけで成り立つわけではありません。
実践するには以下のようなポイントがあります。
- 情報収集を怠らない
→判断は情報の質と量に左右されます。必要なデータや意見を集め、偏った視点にならないよう心がける必要があります。 - 目的を明確にする
→「何のためにこの選択をするのか」を言語化することで、迷いが減ります。 - 小さな選択から始める
→いきなり大きな決断を迫られると負担が大きいため、日常の小さな場面で主体的に選ぶ練習を重ねます。 - 責任を受け入れる覚悟を持つ
→自分で決めた以上、その結果にも責任を持つ姿勢が必要です。
注意点
自己決定性は強力な武器ですが、行き過ぎると孤立や自己中心的な行動につながる恐れがあります。
我が強いとは違うというのでバランスをとるのは難しいかもしれません。
- 周囲の意見を無視しない
- 「自分が正しい」という思い込みにとらわれない
- 他者の課題に過剰に介入しない(課題の分離とのバランス)
アドラー心理学では、自分の選択を大切にしつつも、他者との協力や共同体感覚を忘れないことが強調されています。
まとめ
自己決定性は、自分の人生を自らの意思で切り開くための重要な力です。
職場でも私生活でも、主体的な行動や課題解決能力の向上に直結します。
ただし、独断的にならず、周囲との関係性を保ちながら選択することが成功の鍵です。
日常の小さな選択から練習を始め、徐々に大きな決断にも自信を持って臨めるようになれば、自己決定性は人生のあらゆる場面であなたを支えてくれるはずです。
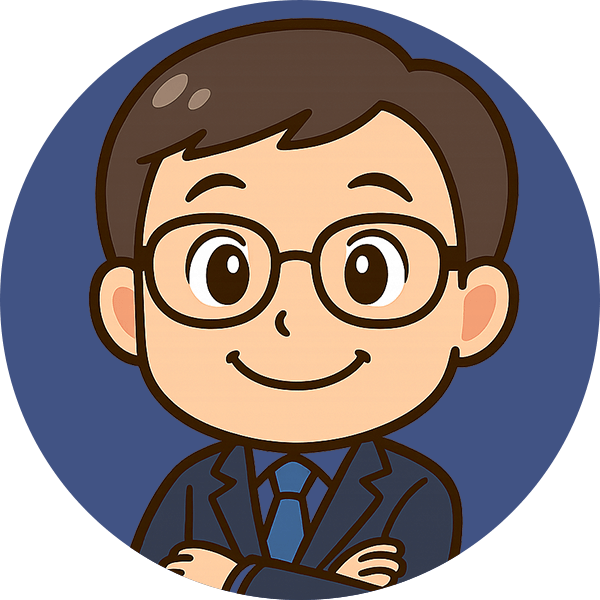
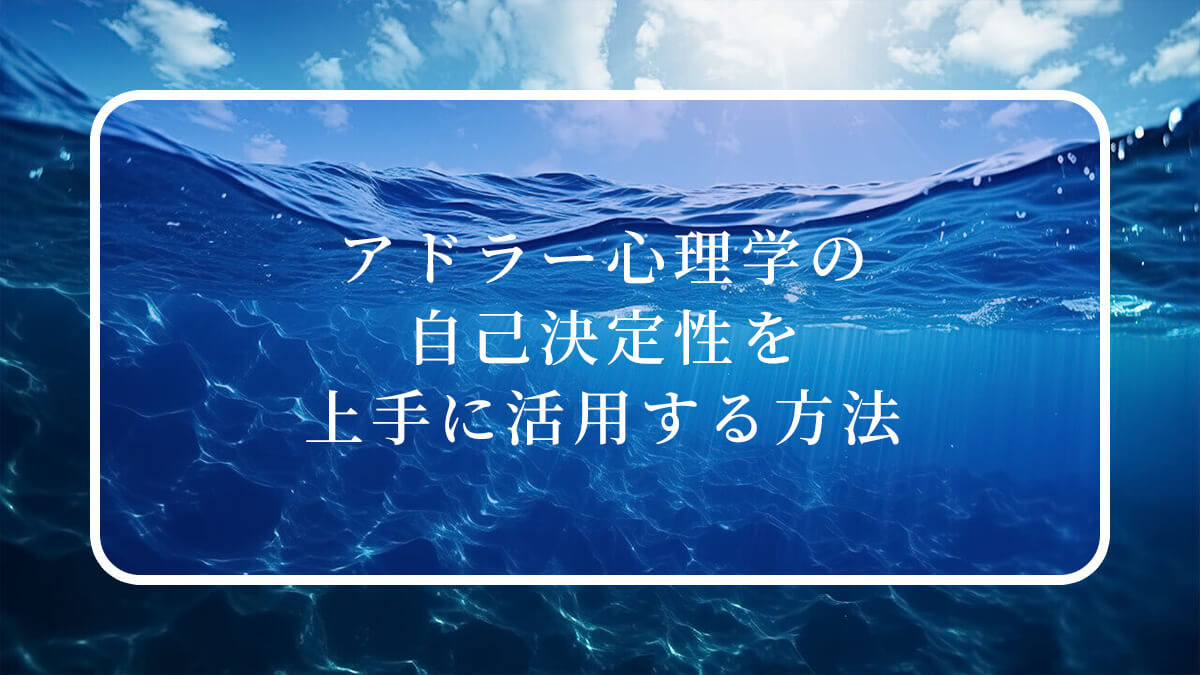
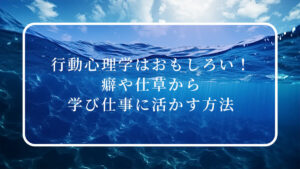
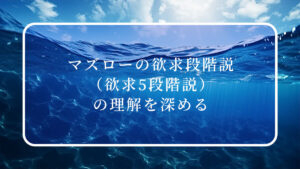
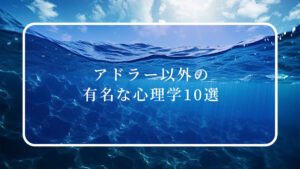
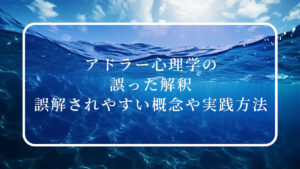
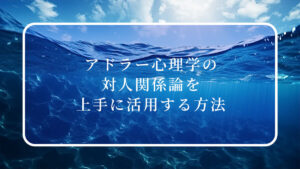
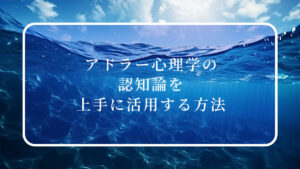
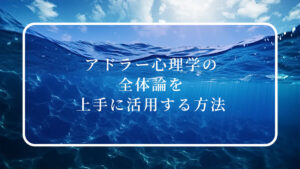
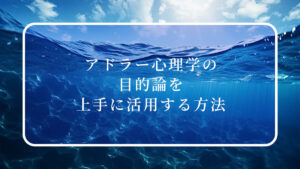
コメント