アドラー心理学を誤った解釈をしている人は結構いるかもしれません。
その概念や実践方法は誤解されやすいことも相まって、意識しているつもりが全く違った行動をとってしまう。
誤解を生みやすい概念、実践の難しさ、そして他者からの影響などの要因から、本記事ではその事例をまとめて何が間違ってるのかを解説していこうと思います。
アドラー心理学が誤解されやすい理由
アドラー心理学は「嫌われる勇気」などのベストセラーによって広く知られるようになりましたが、その一方で一部の言葉だけが切り取られて拡散される傾向があります。
SNSや短い記事で見かける場合、理論の背景や前提条件が省かれるため、意味が変わってしまうことも多いと思います。なので余計間違った解釈をされてしまうわけですね。
また、アドラー心理学は一見シンプルに見えるのも誤解の温床です。
「過去ではなく目的に着目する」「他人の課題には踏み込まない」など、短いフレーズにまとめられるため、深く理解しないまま「こういうことだろう」と自己流の解釈で行動してしまうケースがあります。
さらに、理論と実践の間にはギャップがあり、頭では分かっていても感情が追いつかないことも誤解を招く原因です。
誤解されやすい代表的な概念と間違った解釈
代表的な誤解のひとつが課題の分離です。
本来は「自分の課題と他人の課題を区別し、それぞれが自分の責任で対処する」という考え方ですが、「他人のことは一切関知しない」「困っていても放っておく」といった冷淡な行動にすり替えられることがあります。
結果として、関係を断つことを正当化する理由にされてしまうのです。
簡潔的に解釈しがちな性格だったりすると、間違った解釈をしやすいかもしれません。
目的論もよく誤解されます。
アドラー心理学では、行動や感情には必ず何らかの目的があると捉えますが、「過去を振り返らない=反省しない」と混同されがちです。
実際は、過去を否定するのではなく、過去の出来事をどう解釈して今の行動に活かすかが重要です。
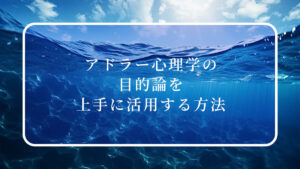
共同体感覚は、全員と仲良くしなければならないという意味ではありません。
誤解された場合、「意見の対立を避けるために自己主張をやめる」「表面的な調和を保つことが最優先」という行動につながり、結果的に本来の目的である相互尊重が失われます。
また、勇気づけも単なるおだてや無根拠なポジティブ思考として扱われることがあります。
本来は相手の価値を認め、失敗や困難に向き合う力を引き出すための行動ですが、表面的な「褒め言葉」に終始すると効果はなく、むしろ信頼を損なうことさえあります。
誤解を招く実践方法の例
実践の過程で誤解が生じることも少なくありません。
特に、書籍やSNSで得た断片的な情報をそのまま日常に適用すると、自分に都合の良い形で理論をねじ曲げてしまうことがあります。
たとえば「課題の分離」を学んだ人が、家族や同僚との問題から距離を置く口実にしてしまうケース。
表面的には理論を守っているように見えても、実際は責任回避や感情の回避になっていることがあります。
さらに、人は自分の経験や価値観というフィルターを通して物事を解釈します。
そのため、「勇気づけ」を「相手を傷つけないための優しい言葉」とだけ捉え、必要なときに厳しい意見を避けてしまうことも。
結果として、相手が本来成長できる機会を奪ってしまうことになります。
誤解を減らすためのアプローチ
まず、信頼できる原典や専門家の解説に触れることが大切です。
日本語での解説本や講座は多数ありますが、著者の理解度や解釈によって内容が異なるため、複数の資料を参照すると誤解のリスクが減ります。
また、ひとつの概念を複数の事例で学び直すのも有効です。
同じ「課題の分離」でも、職場・家庭・友人関係では適用の仕方が異なります。
実践の場を変えて試し、うまくいかなかったときはその理由を振り返ることで理解が深まります。
他人からのフィードバックも欠かせません。
自己流の解釈で行動していないか、信頼できる人に率直な意見をもらうことで、理論のズレを修正できます。
さらに、「理論→行動→振り返り」というサイクルを継続的に回すことで、理解と実践の精度が高まっていきます。
まとめ
アドラー心理学は実践的で、日常生活や仕事の場面に活かしやすい魅力的な理論です。
しかし、その簡潔さゆえに誤解されやすく、表面的な理解で終わると逆効果になる可能性もあります。
誤解を避けるためには、まず正確な理解を持ち、自分の行動や考え方が理論に沿っているかを客観的に確認すること。
そして、一度身につけたと思っても、状況や相手によって応用の仕方を見直す柔軟さが求められます。
アドラー心理学の本質は、人間関係をより良くし、個人が主体的に生きるためのものだと思います。
私もまだまだ勉強中の身ですので、何度も繰り返しながらこまめに再確認して実践していくのがいいのかなと思います。
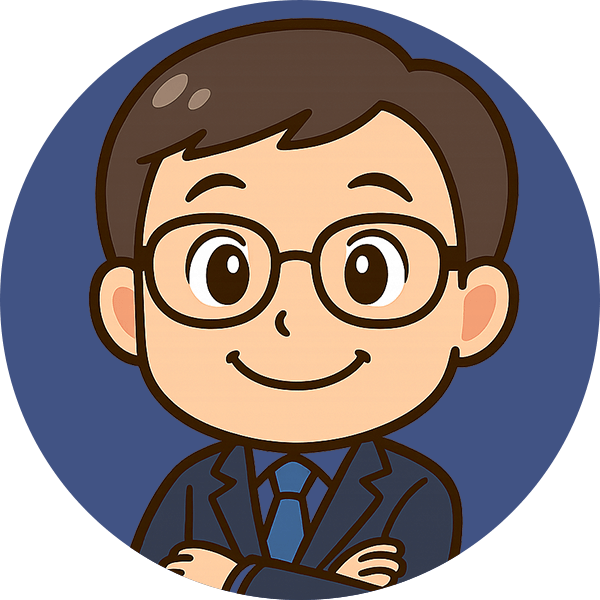
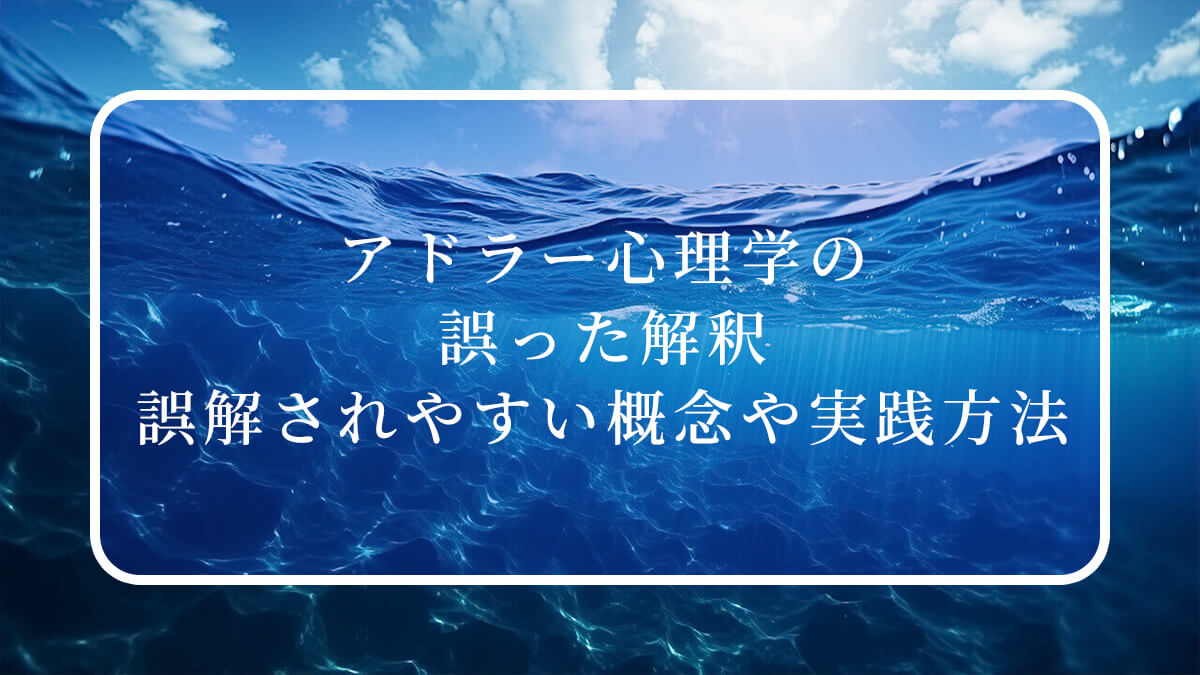

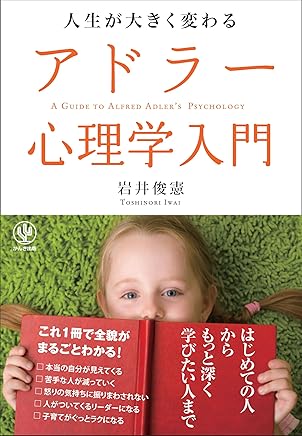
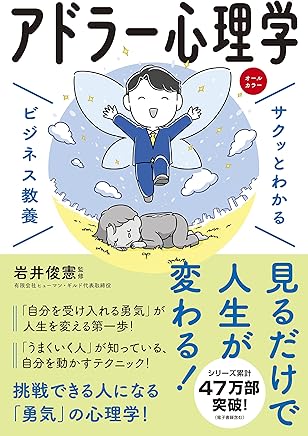


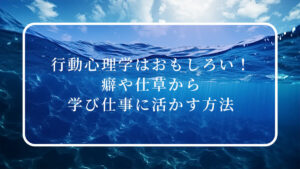
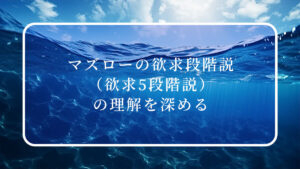
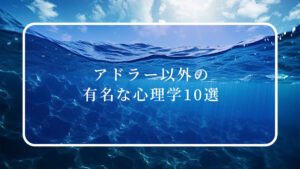
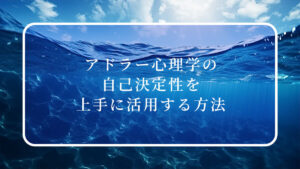
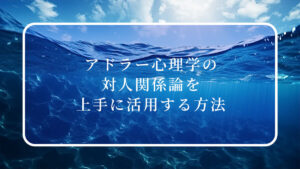
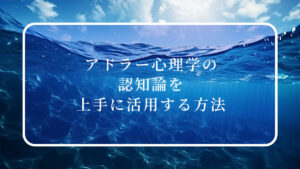
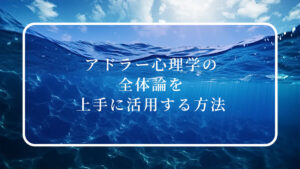
コメント