人間関係は、誰にとっても悩みの尽きないテーマです。職場や家庭、友人関係など、日々の生活の中で「どうすればもっと円滑に関われるのか」と思い悩むことも多いのではないでしょうか。
そんな中で、最近よく耳にする「アドラー心理学」という考え方に注目してみました。
名前は聞いたことがあるけれど、実際にどんな内容なのかはよく知らないという方も多いと思います。
そこで今回は、アドラー心理学を通して人間関係に活かせるヒントがあるのかどうか、自分なりに調べ、まとめてみました。
アドラー心理学とは?
アドラー心理学は、オーストリアの精神科医アルフレッド・アドラー(Alfred Adler)によって提唱された心理学の体系です。
正直なところ、僕は心理学の専門家ではありません。ただ、日々の人間関係に悩みながら、少しでもより良くできる方法はないかと調べていく中で、アドラー心理学という考え方が話題になっていることを知りました。もうかなり前の話です。
アドラー心理学は専門用語や難解な理論ではなく、実生活にすぐ応用できるような、シンプルで実践的な考え方が多く含まれていることも話題になった理由なんだと思います。
アドラー心理学の根本には、「人は変われる」「人は自らの意思で人生を選択している」という前向きな思想があります。この考え方は、一見するとシビアにも思えるかもしれませんが、「自分の人生に責任を持ち、自らの力でより良くしていくことができる」という点で、多くの人に勇気を与えてくれるものです。
たとえば、「過去のトラウマが今の自分を形作っている」という一般的な心理学の見方に対し、アドラーは「人は目的に向かって行動している」と考えます。つまり、過去に何があったかよりも、「これからどうしたいのか」「今どんな目的を持っているのか」の方が重要なのです。
さらに、アドラー心理学では「すべての悩みは人間関係の悩みである」と言われます。僕たちが日々感じるストレスや不安の多くは、実は他人との関係性の中から生まれているという指摘です。この一文だけでも、アドラー心理学が人間関係にどれほど深く切り込んでいるかが分かると思います。
また、アドラー心理学の実践的なアプローチとしてよく紹介されるのが、「課題の分離」という考え方です。これは、「自分の課題」と「他人の課題」を明確に分けることによって、無用なストレスや干渉を避けるという方法です。相手の感情や行動をコントロールしようとするのではなく、「自分ができること」「自分の責任範囲」に集中することで、精神的な自由が得られるという考え方です。
このように、アドラー心理学は「理論」よりも「実践」に重きを置いており、哲学的な思想と日常の行動を結びつける点で、他の心理学とは少し異なる立ち位置にあるように感じます。
アドラー心理学における人間関係の特徴
アドラー心理学の中で人間関係はとても重要なテーマです。というのも、前述のように「すべての悩みは人間関係の悩みである」とアドラー自身が語っているからです。
まず、アドラー心理学では「対等な関係性」が重視されます。これは、上下関係や支配・服従といった構図ではなく、お互いを尊重しあうフラットな関係を築くことを目指すという意味です。たとえば、親子関係であっても「子どもを一人の人間として尊重する」「親だからといって偉いわけではない」という考え方がベースになります。
また、「承認欲求を手放す」というのも人間関係において重要な視点です。他人にどう思われるか、どう評価されるかにとらわれすぎると、自分らしく生きることができなくなってしまいます。アドラーは「他者の評価を気にするのではなく、自分がどうありたいかを重視すべきだ」と説いています。
もうひとつ特徴的なのが、「貢献感」の重要性です。人は誰かの役に立っていると実感できるとき、最も幸福を感じるという考え方です。つまり、人間関係の中で「誰かに貢献している」という感覚が、自尊心や自己肯定感を高める鍵となるのです。
人間関係におけるアドラー心理学の活かし方
では、実際にアドラー心理学をどう人間関係に活かせばいいのでしょうか。
ひとつの方法は、「課題の分離」を意識することです。たとえば、職場で同僚が不機嫌で話しかけても返事がそっけない場合、それを「自分のせいかも」と考えて悩むことがあるかもしれません。しかし、アドラー心理学では「その人の感情はその人の課題」であり、自分の課題ではないと捉えます。自分が丁寧に接しているのであれば、それでよし。相手がどう反応するかは相手の責任という考え方です。
また、「承認欲求を手放す」ことも実践的です。SNSの「いいね」の数に一喜一憂したり、職場での評価ばかりを気にしたりしていると、自分が本当にやりたいことや、自分の価値を見失ってしまうことがあります。自分の行動が誰かにどう評価されるかよりも、「自分が納得しているか」「自分が貢献できたと思えるか」に軸足を置くことで、より健やかな人間関係が築けるようになるのです。
そして何よりも、相手を「変えようとしない」こと。アドラー心理学では、「人は変えられない。変えられるのは自分だけ」と考えます。だからこそ、他人を自分の思い通りに動かそうとするのではなく、自分の行動を変えることで環境を変えていくという発想が必要になります。
まとめ
アドラー心理学は、一見シンプルな考え方ですが、その中には深い人間理解と実践的な知恵が詰まっています。僕のように専門的な知識がなくても、「人との関係に向き合う姿勢」の意識を変化させることができます。
対等な関係を築くこと。承認欲求から自由になること。課題を分離し、必要以上に他人の感情に振り回されないこと。
これらはすべて、他人を遠ざけるための方法ではなく、「よりよく関わるための距離のとり方」なんだと思います。人間関係に悩みやすい方ほど、アドラー心理学の考え方を知ることで、少しずつ生きやすさを実感できるかもしれません。
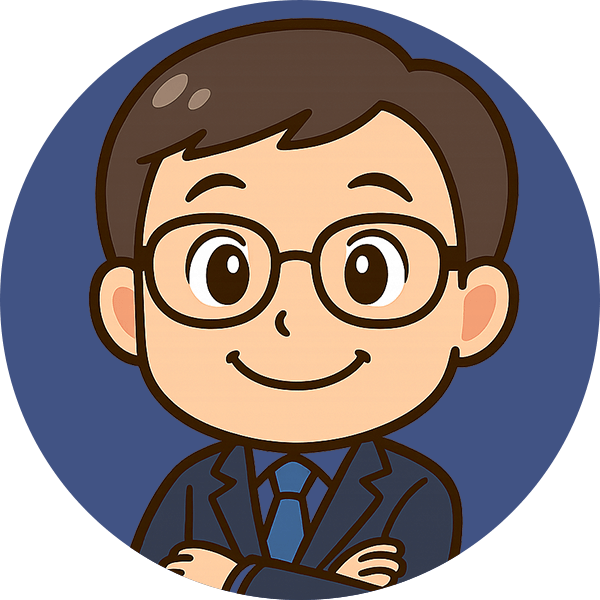
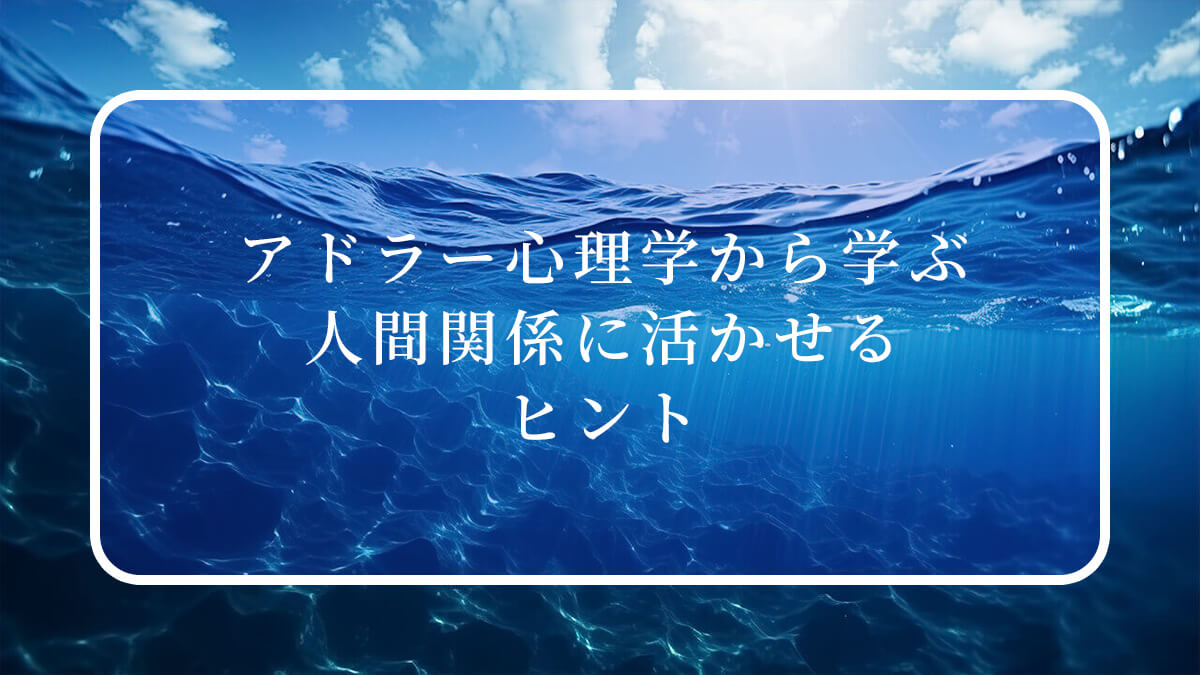
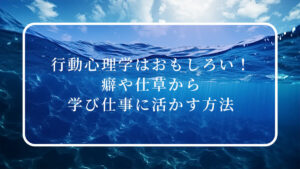
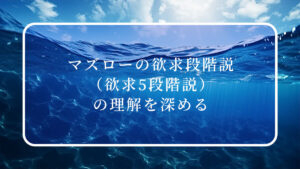
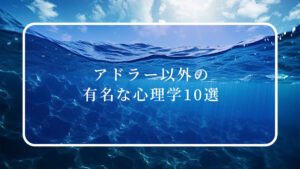
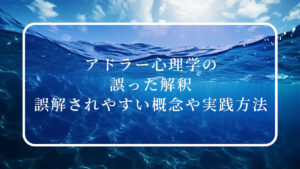
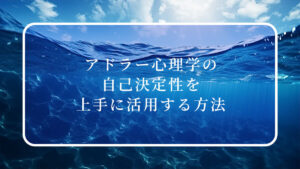
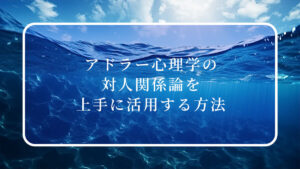
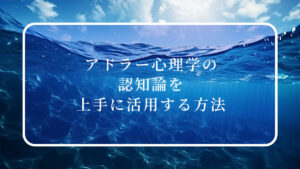
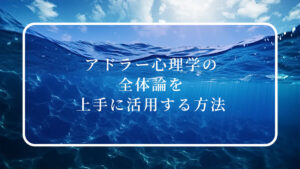
コメント