- 会話中に相手の顔色をうかがってしまう
- 「怒ってる?」「つまらなそう?」とつい考えてしまう
- そのせいで自分の言葉や行動がぎこちなくなる
私を含めこれらをよく気にしてしまう人がいると思います。
相手の表情を気にするあまり、自分のペースを崩してしまう人は少なくありません。仕事の場面でも、友人との会話でも、恋愛でも、「相手は今どんな気持ちなのか?」が頭を支配してしまうことがあります。
この記事では、仕事・友人・恋愛の観点から「相手の表情が気になって仕方がない人」の特徴や心理的理由、そのときの思考の流れをまとめます。
仕事の場面での特徴と心理
仕事では、上司や取引先など立場が上の相手の表情を気にしがちです。プレゼン中に相手が眉をひそめただけで「内容がまずかったのかな」「もう評価が下がったかもしれない」と早合点してしまうこともあります。
これは「評価される立場」にいるという緊張感や、失敗を避けたい気持ちが背景にあります。表情を読み取ること自体は悪くありませんが、読み取りが過剰になり、自分の発言や行動を必要以上に控えてしまう傾向があります。
友人関係での特徴と心理
友人同士でも、相手が少し無表情になると「怒らせた?」と不安になる人がいます。特に、相手を楽しませようとするタイプや場の空気を重視する人に多い傾向です。
この場合の思考は、「相手の機嫌=関係性の安定」と結びついていることが多く、相手の笑顔が減ると自分が否定されたような感覚になります。
恋愛での特徴と心理
恋愛ではさらに敏感になりやすく、LINEのやり取り中やデート中に少しでも相手の表情が硬くなると「もう気持ちが冷めたのかも」と考えてしまうことがあります。
恋愛感情が強いほど、相手の感情の変化に影響を受けやすく、安心と不安の落差が激しくなります。頭の中では「私のせいでこうなった」という原因探しが始まり、会話に集中できなくなることもあります。
なぜ表情が気になるのか?
この傾向は、自己肯定感の低さや、過去の経験が影響していることがあります。
たとえば「人の顔色をうかがわないとトラブルになる」という環境で育った人は、そのスキルが習慣化します。
また、相手の感情をコントロールできると思い込んでいる場合もあり、「自分が何とかしなければ」という責任感が過剰に働くケースもありそうです。
思考の流れの例
- 相手の表情が少し変わる
- 「今の反応はネガティブかもしれない」と推測
- 「自分の発言や態度が原因かもしれない」と自己原因化
- 態度を変えたり、場をつくろうとする
- 余計にぎこちなくなる
まとめ
相手の表情を読む力はコミュニケーションにおいて重要ですが、過剰になると自分の行動や思考を制限してしまいます。
大切なのは、相手の表情の変化を「確定的な事実」と捉えず、「一つの情報」にとどめること。
感情の推測に頼りすぎず、会話そのものに意識を向けることで、必要以上に振り回されることを防げるかなと思います。
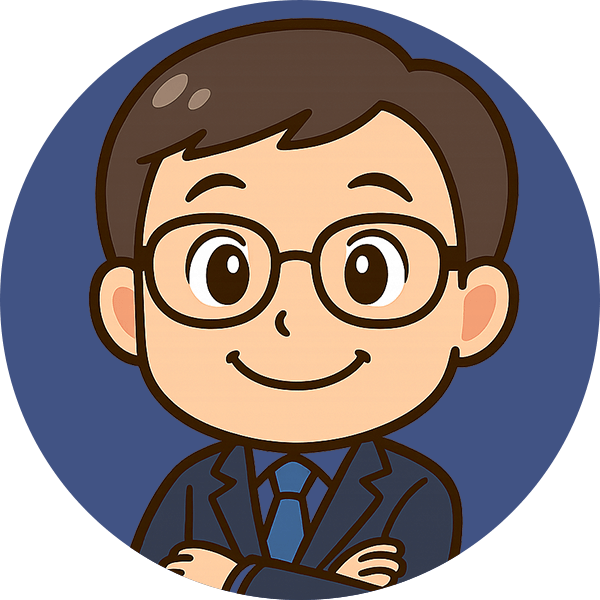

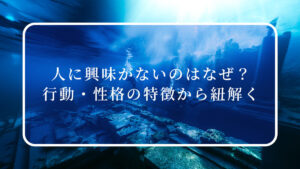
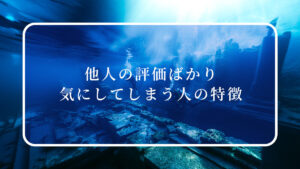
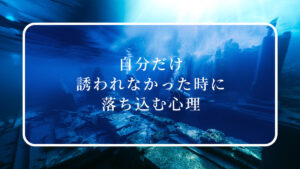
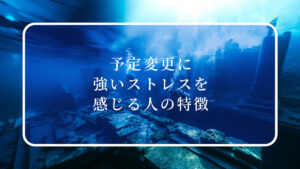
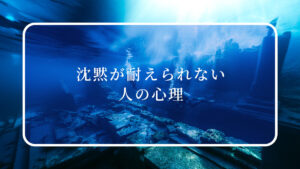
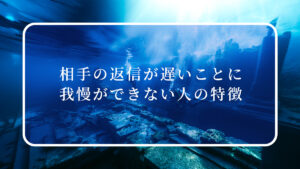

コメント