職場やサークル、趣味のグループなど、集団行動の場では「空気を読み、自然に溶け込み、そこにいるのが当たり前になる」人がいます。一方で、どれだけ距離を縮めようとしても馴染めず、いつの間にか場の輪から浮いてしまうと感じる人もいます。
この記事では、なぜ「グループの空気に自然と馴染めない人」がいるのか、その心理的な背景や特徴を掘り下げています。そして、自然と馴染むのではなく意識や工夫が必要な場合もある、という視点から問題を整理しました。
グループの空気に馴染めない人の特徴
挨拶や会話の反応が薄い
周囲が交わす軽い挨拶や雑談に対して、反応や態度が控えめだと、「興味がない」「付き合いたくない」と誤解されやすく、輪に入りづらくなることがあります。
自分のペースと感性を大切にしたい
場の空気に自然と合わせず、自分なりの一貫したペースを守ろうとする傾向があります。そのため、周囲との“テンポ感”にずれが生まれ、馴染みにくくなります。
空気を読むのが苦手(または過度に読みすぎて疲れる)
場の空気や他者の期待を感じ取りにくい、または意識しすぎて疲れるタイプです。前者は自然と浮いてしまい、後者は合わせようとするほど心が疲弊し、元気がなくなります。
感受性が強く細かな違和感に敏感
視線、声のトーン、間の空気、といった微細な刺激に反応しやすく、それが負担になる人もいます。雑談や行動のリズムに自分を合わせにくく、疲れやすい傾向があります。
自己意識が強く自己表現が控えめ
自分がどう見られているかを意識しすぎると、発言や行動に遠慮が生まれ、本音を出しづらくなります。結果として、個性が見えづらく、周囲に馴染みにくい印象を与えてしまうことがあります。
集団行動との関係――なぜ簡単に解決できないのか?
同調圧力と無意識のルールが壁になる
多くの集団には明文化されない“暗黙のルール”があります(昼休みを一緒にとる、帰る前に声をかけるなど)。これに気づきづらいと、「常識が合わない」「馴染めない」と感じられます。
初期の「居心地」が後の関係性を左右する
最初の数週間に受けた印象が長く影響する「初期印象効果」があります。歓迎されていないと感じると、自分から壁を作ってしまいやすく、その後の関係が築きにくくなります。
精神的安全性がない場で無理は負担になる
自由に意見を言えない、質問しても否定される環境では、「場に馴染む」ための努力はむしろストレス。自己表現が抑えられることで、自分自身も居場所を感じにくくなります。
簡単に解決できないのは“個人の性格”と“環境”の両方が絡むから
性格的特徴もあれば、組織やグループの文化的背景も影響します。本人の改善だけでなく、グループ側の受け入れ態勢や柔軟性が整っていなければ、馴染むのは難しいケースが多いです。
「一人でいることが好き」とは違うタイプ
一人の時間が好きな人は、正確に言えば「自分で何をするかを自由に選べる独立した時間」を気軽に認めている人たちです。集団に馴染めないのとは違い、「選択して一人を楽しんでいる」点が大きく異なります。
それに対して「集団に馴染みたい」のにどうしても出来ない人は、本当は他人との関わりを欲しているけれど、その場の空気やペースに適合しづらいため、結果的に隔離を覚えてしまう種類の一人です。
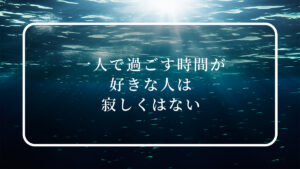
まとめ
グループの空気に馴染めないと感じるのは、個性や空気読みの問題だけではなく、集団側の期待値や構造にも影響されます。
大丈夫。馴染めないことは失敗ではなく、そこにある空気に自分が適合していないだけです。自分に合った空気や種類を見つけていけばいい。
「一人で過ごす時間」を適度に並行させながら、無理のない人間関係を尋ねることで、自分らしい空気を作りだせるようになるかもしれません。
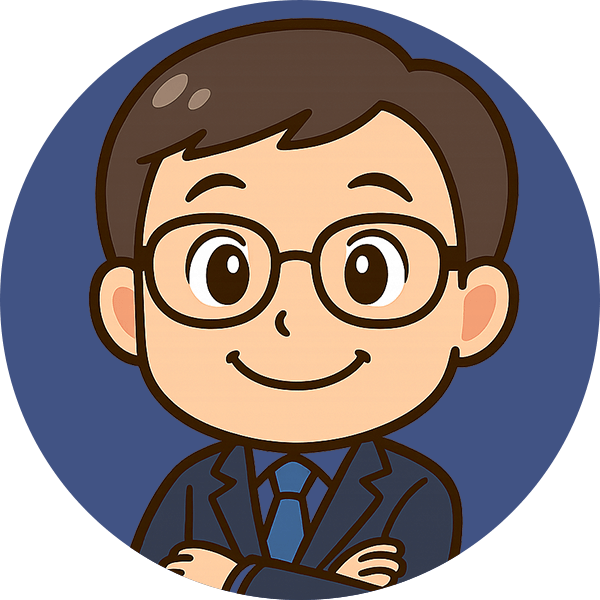
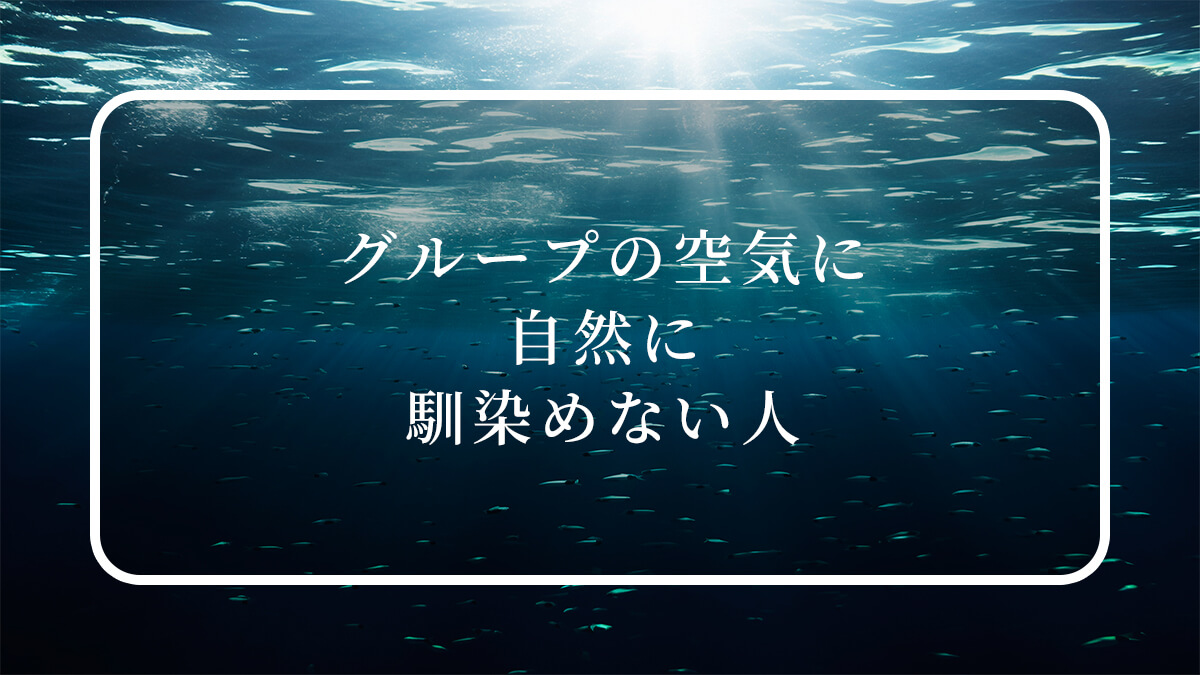
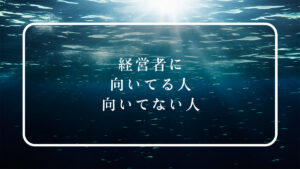
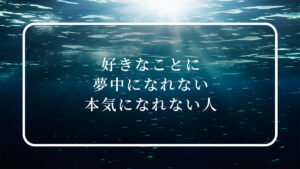
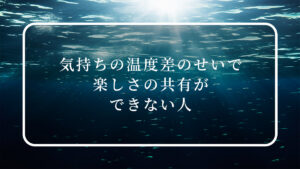
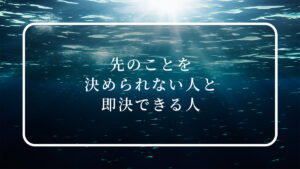
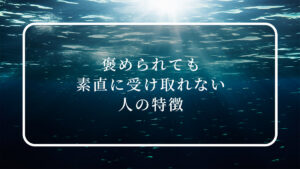
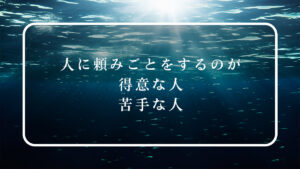
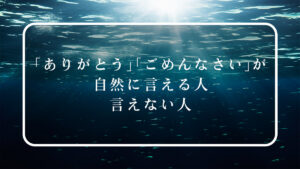
コメント