多くの人が趣味や情熱に没頭して、自分の時間を充実させている姿を見ると、ふと自分はどうしてそこまで全力で好きになれないのだろう…と感じることはありませんか?たとえ好きなことがあっても、どこか距離感があって、熱中できない、自分も本気で取り組めない…そんな感覚に悩む人も少なくありません。
今回は、なぜ「全力で好き」になれないのか、その心理的な背景と、夢中になれるものを見つけるヒント、そして夢中になることの意義まで、幅広くまとめてみました。
夢中になれない原因
情熱や没頭にブレーキがかかる原因
- 心身の疲労・ストレス
心身が疲れていると、趣味や好きなことに取り組む気力が湧きにくくなります。義務感や日々のタスクに追われて、「好きなことを楽しむ余裕」を失っているケースも多いです。 - 完璧主義や成果へのプレッシャー
「本気になったら結果を出さなければ」と思いすぎて、自分の楽しみが義務や重圧に変わってしまうと、自然な情熱が枯れてしまいます。 - フロー体験の不欠如
心理学者チクセントミハイの「フロー理論」によれば、夢中になるには、スキルと課題の難易度が適切に一致している状態=「没入できる状態」が必要ですが、それが整っていないと没頭できません。 - 挑戦のハードルが高すぎる/成長実感なし
難しすぎる目標や、進歩を感じられない環境では、やる気が続かず没頭できません。「どうせ自分には無理」と思ってしまう瞬間に情熱は途切れがちです。 - 自分に制限をかけている思い込み
自身が「好きなことに本気になる資格がない」「無駄かもしれない」と無意識にブレーキをかけてしまい、心の中で夢中になる動機を潰してしまうこともあります。
夢中になれることを見つける方法
小さく始めてみる(試行錯誤型アプローチ)
まずは、気になる活動を軽く手を付けてみる。「有料でなくてもよい」「過度な期待はしない」といった軽い気持ちで始めることで、自然に継続できる可能性があります。
好奇心や興味からサインを探る
学生時代に好きだったことや、つい時間を忘れて熱中した経験をヒントに、自分が本当に関心を持てる領域を探ってみるのが効果的です。
義務感を外して、遊び感覚で続けてみる
「趣味も仕事も義務化すると楽しめない」という心理に対処するには、気軽に「やってみる」感覚を大事にし、完璧主義や義務感を一度脇に置くことが重要です。
フローを意識した環境づくり
挑戦とスキルのバランスがとれている活動、明確な目標と即時フィードバックが得られるシチュエーションを選ぶことで、没頭できる環境を整えられます。
目標を小さく設定し、成長を感じる
過度に大きなゴールではなく、「今日これだけやる」「前回より少しできた」など、達成感を感じられる目標を積み重ねることで、やる気と没頭感につなげていけます。
夢中になることの重要性
幸福感と自己肯定感の向上
日本での調査によると、「好きなことに夢中になれる活動(推し活など)」がある人は、幸福度や人生満足度が高く、精神的にも豊かな傾向があります。
認知機能の維持や発展にも寄与
趣味を持ち続け、夢中になれる活動に取り組み続けた人たちは、認知機能の衰退が少ないという研究結果もあり、特に高齢期の健康面においても意味があります。
自己表現・自己発見につながる
夢中になれる経験は、自分自身の強みや好み、限界や可能性を知る手がかりとなり、個人の成長や自己理解にも深く関係します。
まとめ
「好きなことに夢中になれない人」は、決して怠けているわけでも、意志が弱いわけでもありません。むしろ、心身の状態や完璧主義、自己制限、環境の不一致などが複雑に絡んでいて、自然な情熱が芽吹く前に止まってしまうことが多いのです。
しかし、夢中になる経験は、幸福感や自己肯定感、集中力の維持につながる大切な活動です。以下のようなステップを通じて、自分に合った「没頭できる何か」を探してみてはいかがでしょうか?
- 小さく始める勇気を持つ(義務感を外す)
- 自分の興味や過去の経験に耳を傾ける
- フロー体験が得られる活動を探す
- 小さな成長や達成感を重ねる
すぐに熱中できない人も、ちょっとした工夫と「自分にはまだ芽吹く可能性がある」という感覚を持てば、好きなことに本気になった未来も決して遠くはないはずです。
って偉そうに言ってますが僕も本気になれないタイプなので人生日々勉強。そして努力ですね。
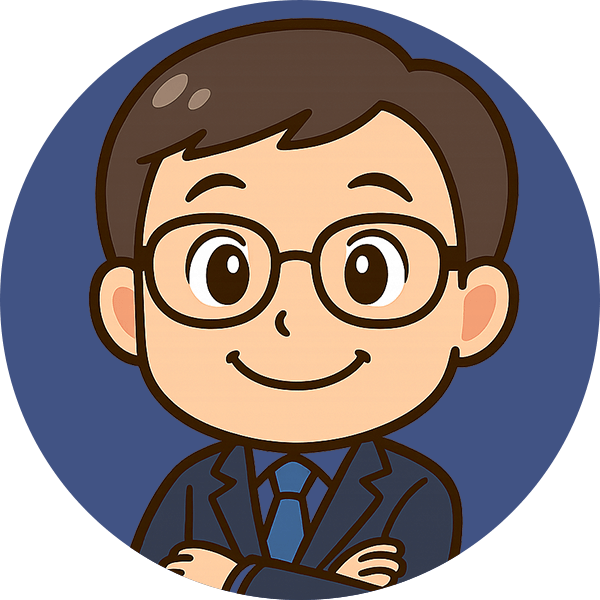
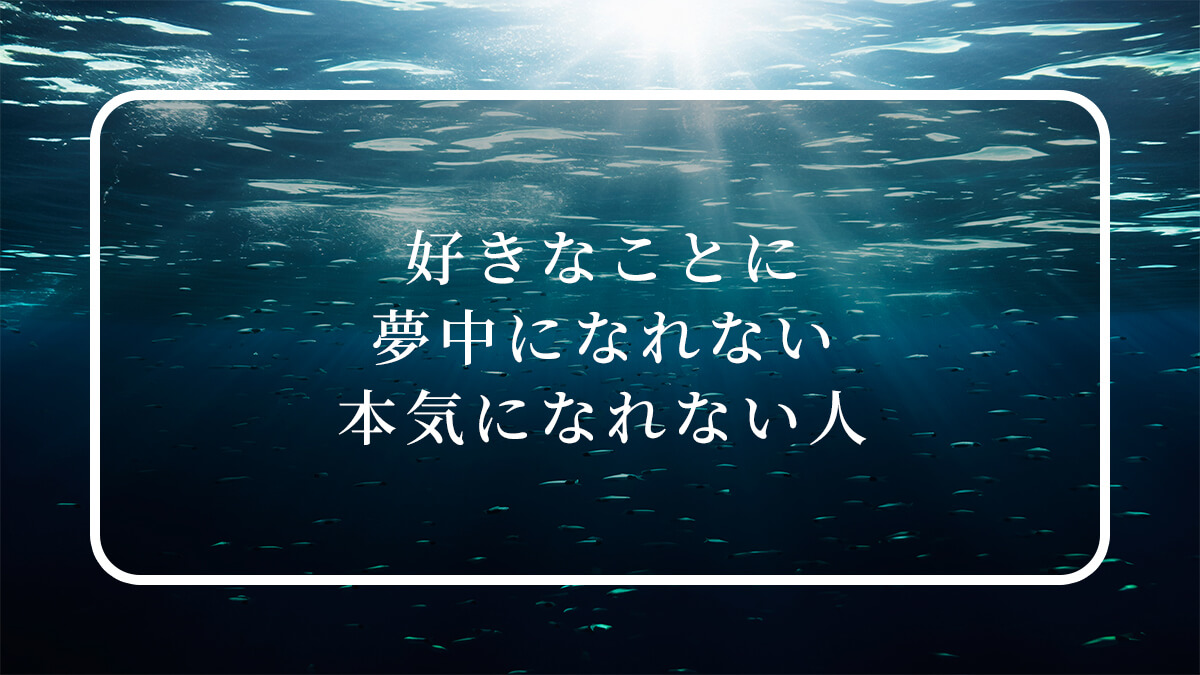
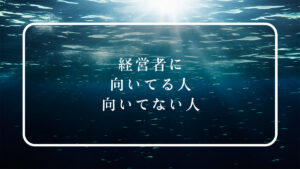
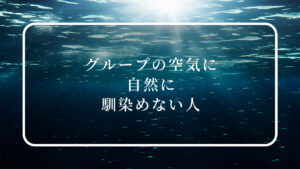
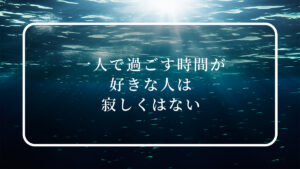
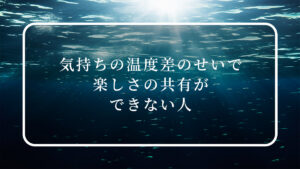
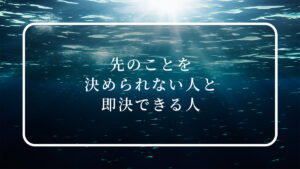
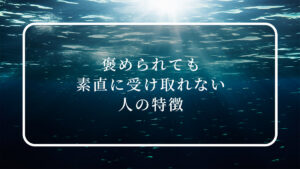
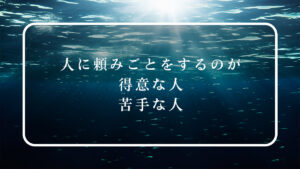
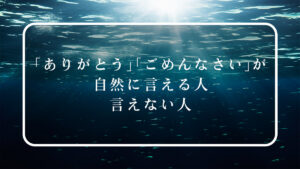
コメント