誰かに褒められたとき、本当は嬉しいはずなのに、「いやいやそんなことはないです…」と返してしまう。
これは謙遜というよりも、心の奥底で「褒められる=受け入れがたい」と感じている人の特徴です。
本記事では、その背景や理由を、日本人に多い心理傾向とともに丁寧に整理しました。
褒められても受け入れられない、謙遜以外の本当の心理
人に頼みごとをすることに抵抗がない人もいれば、僕のように「なるべく自分で全部やろう」と考えてしまう人もいます。
まず、褒め言葉を素直に喜べない人の中心には、自己肯定感の低さがあります。
自分には価値がない、人からの評価はお世辞だと思ってしまい、自分に相応しいとは感じられません。
さらに、褒め言葉をプレッシャーと感じる人もいます。「次も同じ期待に応えなければ」「これ以上失敗できない」と感じ、自分を追い込む一因となります。
また、褒め言葉に裏や条件を疑う傾向もあります。日本では「褒めておいて○○を頼む」「こっそり皮肉が含まれている」と感じてしまう人も少なくなく、純粋な言葉だとは受け取れないケースです。
日本人に多い傾向:謙遜文化と自己価値の低さ
日本では「謙虚であること」が美徳とされる文化が根強く、幼い頃から「褒められたら否定する」「相手を立てるべき」という教育を受けて育つ人も多いです。
そのため、「褒められても素直に喜ぶこと」が恥ずかしい、あるいは図々しいと感じてしまう傾向もあります。
謙遜の文化は、自分の価値を無意識に低く設定してしまいやすく、それが褒め言葉を受け取れない土壌になっているのかもしれません。
心理的特徴と行動パターン
以下に、褒められても素直に受け入れられない人の具体的な特徴をまとめてみました。
自己肯定感が極端に低い
日常的に自己否定しがちで、「褒められる価値が自分にはない」と感じているため、褒め言葉をそのまま受け止められません。
謙遜が習慣化している
「そんなことないです」が口癖のようになり、謙遜することで自分の居場所を保とうとしますが、結果的に自分の価値を下げてしまいます。
裏を読むクセがある
褒め言葉に対して「この後何かあるのでは」「お世辞だろう」と深読みし、その意図を疑ってしまい素直に喜べない。
※これは僕が当てはまってます。
幼少期に褒められた経験が少ない・トラウマとなっている
子どもの頃に褒めても否定された、喜ぶと叱られた経験があると、「褒められると不安になる」深い心理的構造が形成されます。
まとめ
「褒め言葉を素直に受け取れない」原因には、自己肯定感の低さ、謙遜文化、心理的トラウマ、裏読みのクセなどが絡み合っています。これは決して“甘え”や“性格の問題”だけではなく、学習された思考パターンとも言えます。
ただし、そのパターンを知り、自分のクセに気づくことは第一歩です。少しずつでも以下のような意識を持つことで変化は可能です。
- 褒められたら「ありがとうございます」とだけ受け止めてみる
- 「裏があるかも」と感じても、まずは「言ってくれた事実」として受け入れてみる
- 自分にも小さな努力や価値があると認めて、自分を褒める習慣をつくる
褒め言葉を素直に受け取れないのは、感受性が強い人であるとも言えると思います。
治すことでもないと思いますが、意識しすぎないことも重要かもしれません。
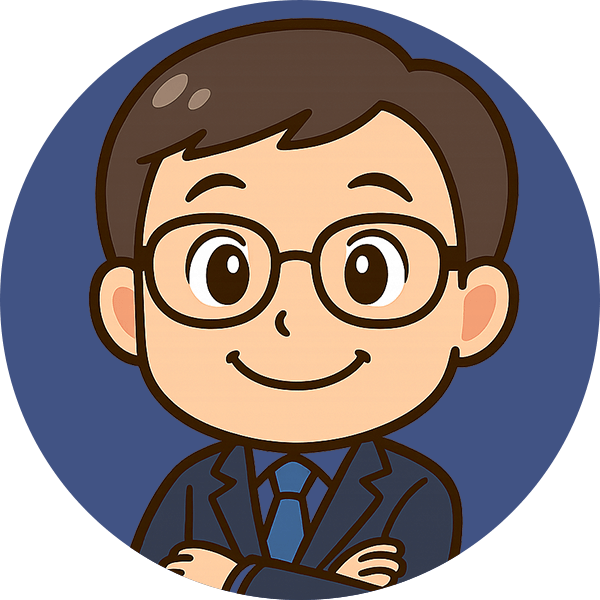
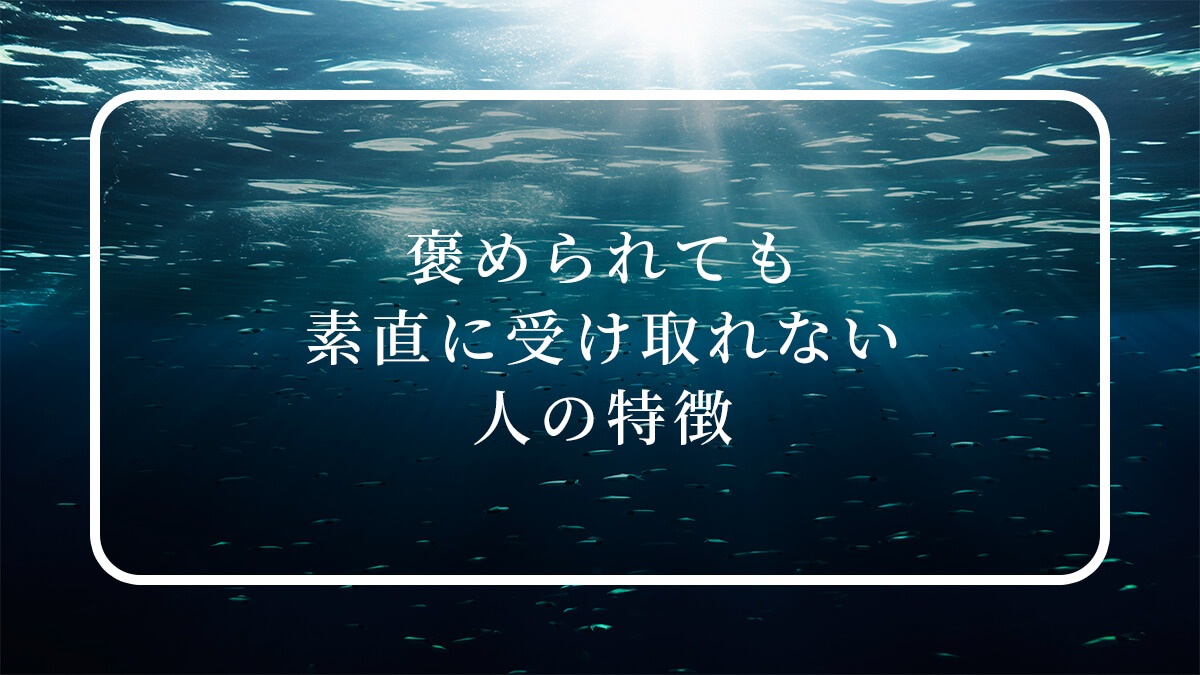
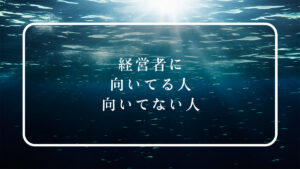
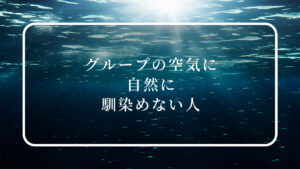
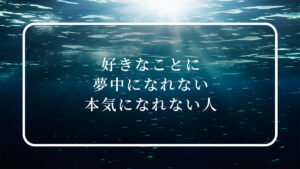
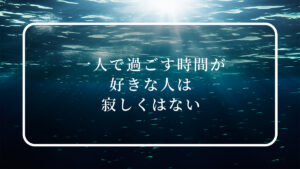
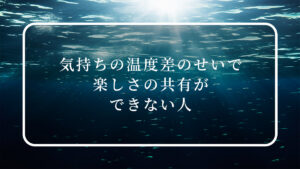
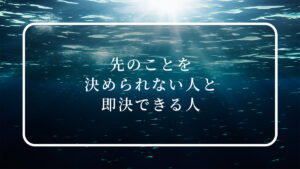
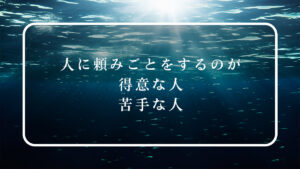
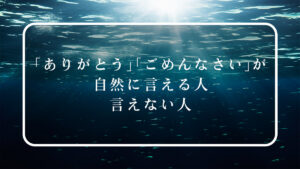
コメント