アドラー心理学の対人関係論は、良好な人間関係を築くための実践的な考え方です。
特に、「課題の分離」「勇気づけ」「共同体感覚」といった概念は、日常生活や職場での対人関係に役立ちます。
これらの概念を理解し、実践することで、より良い人間関係を築き、幸福度を高めることが期待できます。
対人関係論は実際に改善すべきところを意識するには一番いい方法だと思います。アウトプットって結構重要ですからね。
本記事では、いくつか想定できることを考えながら、アドラー心理学の対人関係論を上手に活用する方法をまとめてみたいと思います。
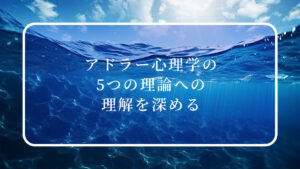
対人関係論の基本概念
アドラー心理学における対人関係論は、人は社会的な存在であり、他者とのつながりの中で成長し、幸福を感じるという前提に立っています。
この理論を支える3つの柱が以下です。
1. 課題の分離
自分の課題と相手の課題を区別し、必要以上に干渉しないという考え方です。
たとえば、友人が資格試験に合格できるかどうかは本人の課題であり、こちらが過度に口を出すべきではありません。
自分の責任範囲を明確にし、相手の課題を尊重することで、余計なストレスや摩擦を減らせます。
2. 勇気づけ
相手の行動や存在を肯定的に評価し、前向きな気持ちを引き出すことです。
これは「褒める」とは違い、結果だけでなく努力や姿勢そのものを認めることが重要です。
たとえば「よくチャレンジしたね」などでしょうか。相手に再挑戦する力を与えるような言葉ですね。相手がどう受け取るかにもよりますが。
3. 共同体感覚
「自分はこの社会に貢献できている」という感覚を持ち、他者とのつながりを意識することです。
これは職場や家庭、友人関係など、あらゆる集団での安心感と信頼感の基盤になります。
日常生活での応用例
対人関係論は、単なる理論として理解するだけでなく、日常生活の中で使ってこそ意味があります。
- 職場でのケース
→部下がミスをした場合、すぐに指示や答えを与えるのではなく、まずは「何が起きたのか」「どうすればよいと思うか」を本人に考えさせる。これが課題の分離の実践です。 - 家庭でのケース
→子どもが宿題をやらない場合、親が代わりにやるのではなく「宿題はあなたの課題」と伝え、結果の責任を本人に持たせる。そのうえで「今日はどこまで進んだの?」などの言葉をかけます。 - 友人関係でのケース
→落ち込んでいる友人に、アドバイスを押し付けるのではなく「あなたの気持ちを理解しているよ」と寄り添い、必要なら行動のサポートを申し出る。これも課題の分離と勇気づけの両方にあたります。
これらは簡単にできてる人もいれば、全くできない人もいます。
私も得意ではありません。部下がミスをした場合、「何が起きたのか」「どうすればよいと思うか」を本人に考えさせたくても現実は考えない人が多く、結局自分でやったほうが早いとなります。
ただ昔であれば落ち込んでいる友人に、アドバイスを押し付けることも多々ありましたが、意外と「ただ聞き役になる」ことも重要だったりします。
活用する際の注意点
対人関係論はとても有効ですが、使い方を誤ると逆効果になることもあります。
- 課題の分離を冷たく感じさせない
→「それはあなたの問題です」と突き放すだけでは、相手との距離が広がります。共感を示しつつ、責任の所在を明確にすることが大切です。 - 勇気づけをお世辞や過剰な励ましにしない
→根拠のない「大丈夫」はかえって不信感を招きます。相手の現状を理解し、努力や過程に焦点を当てて言葉をかけましょう。 - 共同体感覚を押し付けない
→「みんなのために」と強要するのは逆効果です。本人が自然に社会とのつながりを感じられる環境作りが大切です。
まとめ
アドラー心理学の対人関係論は、日々の人間関係をより良くするための実践的な道しるべです。
「課題の分離」で無用なストレスを避け、「勇気づけ」で相手の可能性を引き出し、「共同体感覚」で安心感を育む。
この3つを意識して生活に取り入れることで、自分自身も周囲も心地よく過ごせる関係を築くことが目指せると思います。
理論は知っているだけでは意味がありません。小さな場面から実践し、少しずつ習慣化することで、対人関係は確実に変わっていきます。
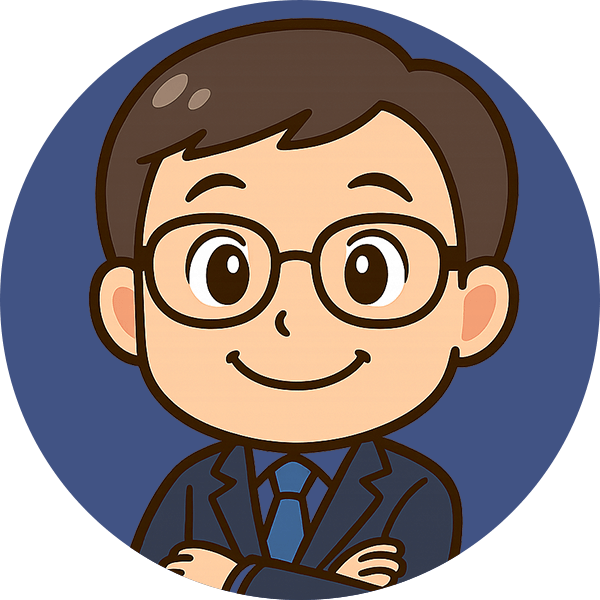
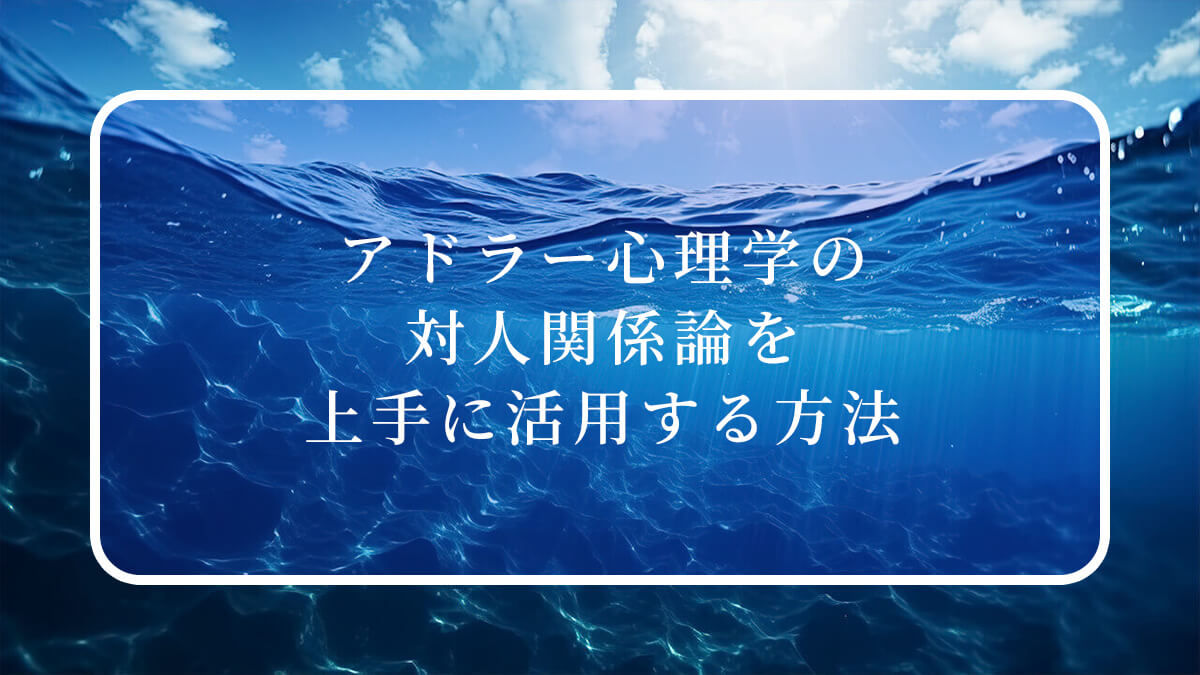
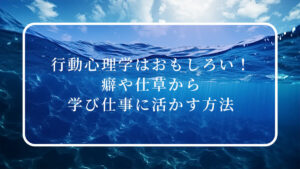
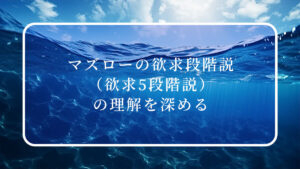
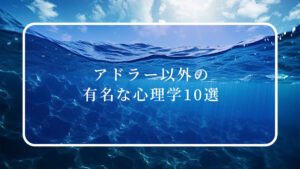
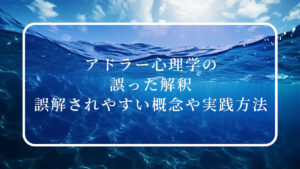
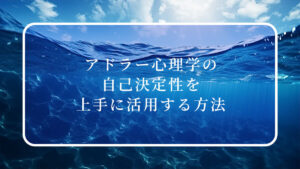
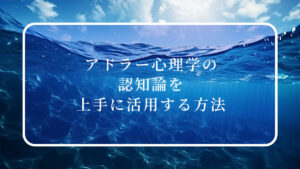
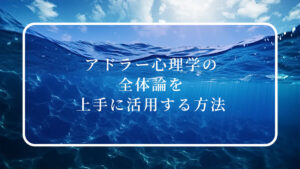
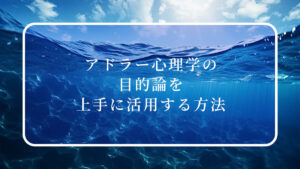
コメント