アドラー心理学の全体論は、個人を分割できない存在として捉え、心、体、理性、感情など、あらゆる要素が相互に影響し合いながら目的達成に向かうとする考え方です。
この全体論を日常生活で活用するには、まず自分の状態を俯瞰的に把握し、各要素(心、体、思考、感情など)をバランス良く改善していくことが重要です。
と、言われてもなんのこっちゃわかりませんよね。最初は時私も全く理解できませんでした。
本記事では、いくつか想定できることを考えながら、アドラー心理学の全体論を上手に活用する方法をまとめてみたいと思います。
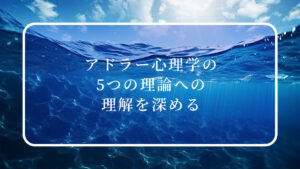
全体論とは何かをもう少し具体的に噛み砕く
全体論の考え方はシンプルです。
人間は「心」「体」「理性(思考)」「感情」という複数の要素で構成されていますが、これらは独立して存在しているわけではなく、密接に結びついています。
たとえば、仕事の納期に追われてストレスが溜まると、夜眠れなくなり(体への影響)、翌日集中力が落ち(思考への影響)、小さなことでイライラしてしまう(感情への影響)、結果として同僚との人間関係まで悪化する(心への影響)。
このように、1つの不調が他の要素にも連鎖して影響してしまいます。
逆に、1つの側面を改善すれば好循環が生まれることもあります。
例えば、適度な運動を取り入れて体調を整えると、頭が冴え(思考)、気分が明るくなり(感情)、人との会話がスムーズになる(心)。
全体論は、この「つながり」を理解し、部分ではなく全体を意識して改善していくアプローチです。
日常生活における全体論の活用例
全体論は特別な場面だけでなく、日常の中でも活用できます。
仕事でのパフォーマンス低下の例
「集中できない」「ミスが増える」と感じたとき、多くの人は思考やスキル不足を疑います。
しかし全体論の視点では、原因が睡眠不足や運動不足、またはプライベートの人間関係のストレスなど、他の要素に隠れていることがあります。
人間関係のストレスの例
友人や同僚とのやり取りで感情が揺れ動く場合、それは感情面だけの問題ではないかもしれません。
栄養不足や疲労、仕事の忙しさによる心の余裕の欠如が、感情の起伏を激しくしていることもあります。
健康とメンタルの相互作用の例
風邪や軽い体調不良が続くと気分が沈みやすくなり、消極的な考え方になってしまいます。
反対に、気持ちが落ち込んだ状態が続くことで体調も崩れやすくなることもあります。
これはまさに、全体論が示す「相互影響」の典型例です。
全体論を取り入れるためのステップ
全体論を実生活に活かすには、次のようなステップが効果的です。
- 現状を4つの側面でチェックする
→「心」「体」「思考」「感情」に分けて、今どの部分が安定していて、どこが崩れているかを書き出します。 - バランスの崩れを見つける
→例:最近はよく眠れているけど、感情面で怒りっぽい → 体は整っているが心や感情が不安定。 - 小さな改善から始める
→いきなり全てを完璧にする必要はありません。まずは1つの側面から整え、連鎖的に好循環を作ることを意識します。 - 波及効果を観察する
→改善を始めてから、他の要素にどう影響が出るかを振り返ります。
全体論の落とし穴と注意点
全体論を意識することで、自分を多角的に見る習慣がつきますが、注意すべき点もあります。
- 完璧主義にならないこと
→全ての要素を同時に整えることはほぼ不可能です。むしろ疲弊してしまうリスクがあります。 - 1つの側面に偏りすぎない
→体調管理に集中するあまり、感情や思考のメンテナンスを怠るとバランスが崩れます。 - 必要に応じて外部の力を借りる
→心理的な問題や体調不良が長引く場合は、専門家の助けを借りることも選択肢です。
まとめ
アドラー心理学の全体論は、「人間は分割できない一つの存在である」というシンプルながら奥深い考え方です。
心・体・理性・感情は常に影響し合っており、一つの変化が全体に波及します。
全てを一度に改善する必要はなく、まずは一つの要素から整えていくことが大切です。
小さな改善が積み重なることで、日常生活や人間関係、仕事の質も自然と向上していきます。
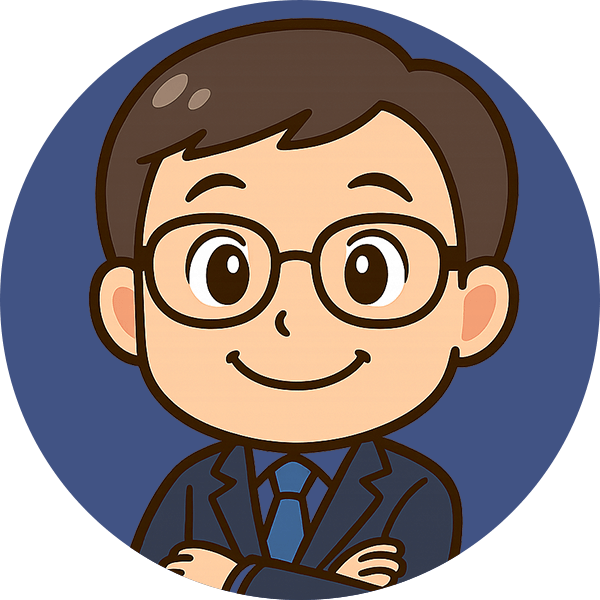
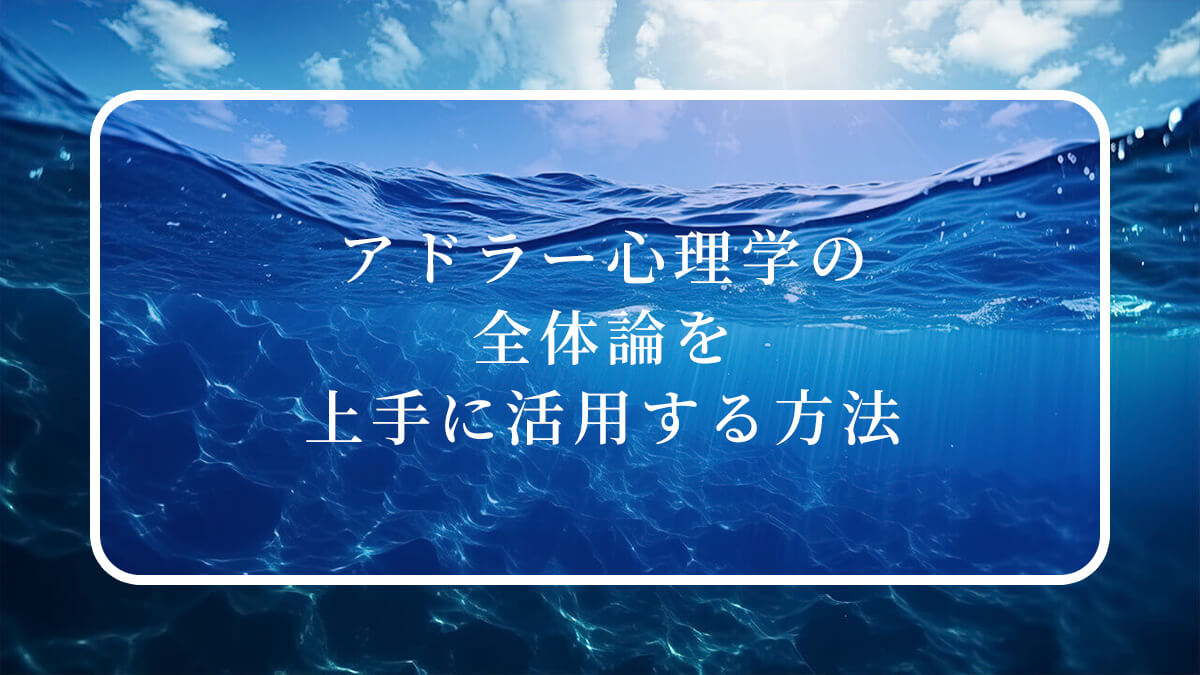
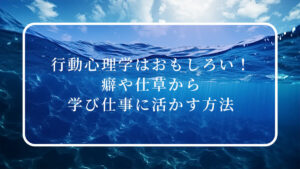
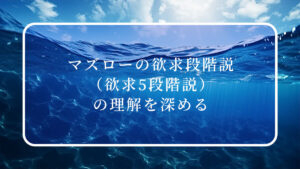
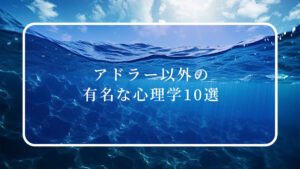
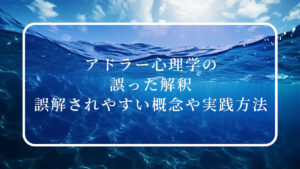
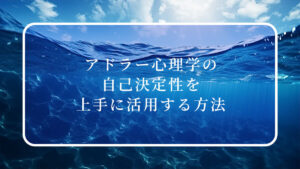
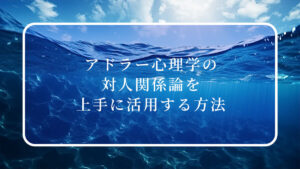
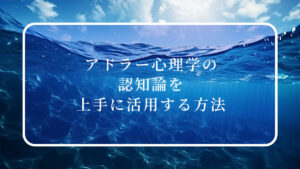
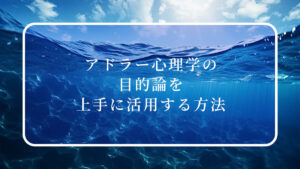
コメント