アドラー心理学の認知論は、物事の解釈の仕方(認知)が行動や感情に影響を与えるという考え方です。
この考え方を活用することで、日常生活や人間関係におけるストレスを軽減し、より良い状態を目指すことができます。
解釈の変更は一見ネガティブからポジティブに変えられそうなものですが、当然すべてがそうではないと思います。
本記事では、いくつか想定できることを考えながら、アドラー心理学の認知論を上手に活用する方法をまとめてみたいと思います。
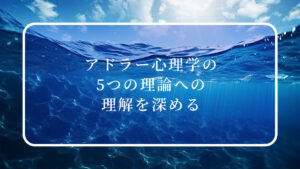
認知論とは何かをもう少し具体的に
認知論の根本にあるのは、「人は出来事そのものではなく、それをどう捉えるかで行動や感情が変わる」という考え方です。
たとえば、上司に「この資料、ちょっと直した方がいいね」と言われたとき、
- 「自分の仕事はダメだったんだ…」と落ち込む人もいれば、
- 「改善のチャンスをもらえた」と前向きに捉える人もいます。
同じ出来事でも解釈が違えば、その後の行動や気分はまったく異なります。
つまり、認知の仕方を意識的に変えることで、人生の質を大きく向上させることができるのです。
日常生活での認知の影響例
認知論は、日常のあらゆる場面で作用しています。
人間関係の摩擦
友人からの返信が遅いとき、「嫌われたのかな」と思えば不安になりますが、「忙しいのかもしれない」と思えば気持ちは穏やかでいられます。
仕事でのフィードバック
注意を「批判」と受け取るか、「成長の機会」と受け取るかで、その後の行動は大きく変わります。
日々の出来事
雨の日を「憂鬱」と感じれば一日中気分は下がりますが、「家で読書を楽しむ日」と捉えれば、むしろプラスの時間になります。
認知を変えるためのステップ
認知の書き換えは、単に「ポジティブに考えよう」とするだけではうまくいきません。
以下のような手順を踏むことで、より自然に行動へつなげられます。
- 出来事と感情を切り分ける
→まずは起きた出来事と、それに伴う感情を分けて整理します。
例:「上司に指摘された(出来事)」→「落ち込んだ(感情)」 - 自分の解釈を書き出す
→「なぜそう感じたのか?」を言葉にします。
例:「自分は仕事ができないと思われたから」 - 別の解釈の可能性を考える
→「他の理由もあり得るのでは?」と視点を広げます。
例:「上司は資料の完成度を上げたかっただけかもしれない」 - 行動の選択肢を増やす
→解釈を変えることで、より建設的な行動を選べるようにします。
認知論を活用する際の注意点
認知を変えることは有効ですが、すべてをポジティブに変換すれば良いわけではありません。
- 現実を否定しない
→問題があるのに「大丈夫」と思い込むと、必要な改善を怠る危険があります。 - 感情を押し殺さない
→ネガティブな気持ちも大切なサインです。感じた上で、どう行動するかを考えることが重要です。 - 他者の立場も考慮する
→自分だけの認知に偏らず、相手の視点からも出来事を見てみることが、人間関係の摩擦を減らします。
まとめ
アドラー心理学の認知論は、私たちが日常で感じるストレスや不安の多くが、出来事そのものよりも「解釈」によって生じることを教えてくれます。
出来事と感情を切り分け、別の解釈を試す習慣を持つことで、より柔軟で前向きな行動を選べるようになります。
ただし、現実から目をそらさず、必要な対処を行うことも忘れてはいけません。
認知論は、日々の生活や人間関係をより快適にするための「思考のメガネ」をかけ直すようなもの。
そのメガネを上手に選び、使いこなすことが、より豊かな人生への一歩となります。
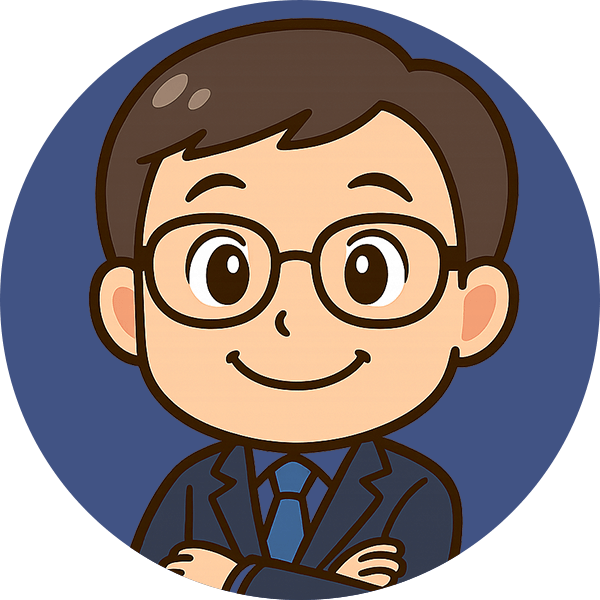
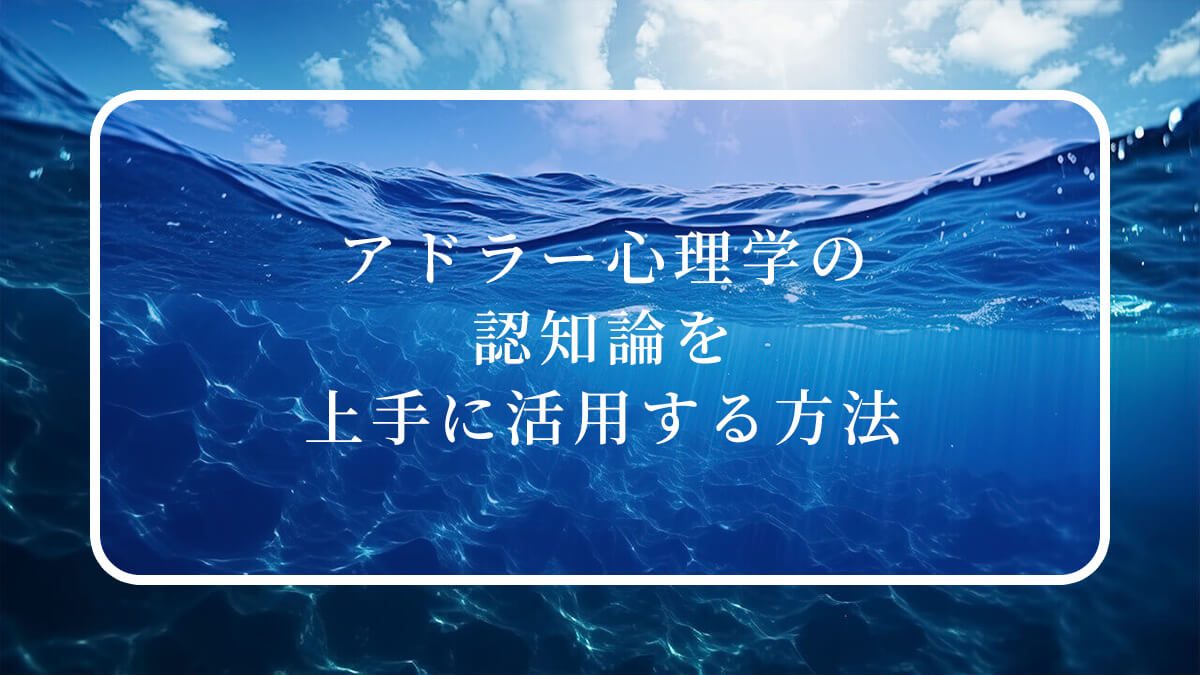
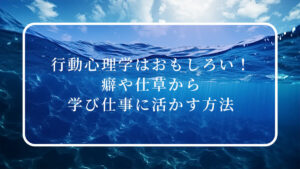
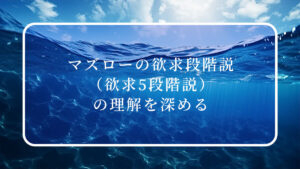
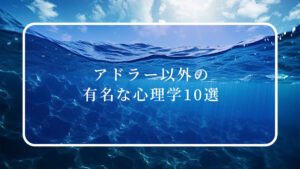
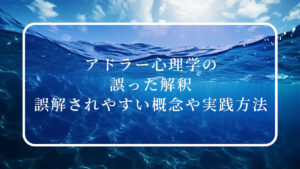
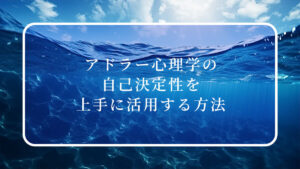
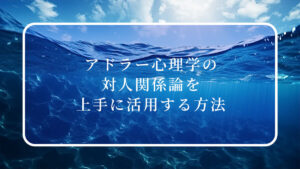
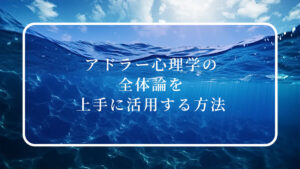
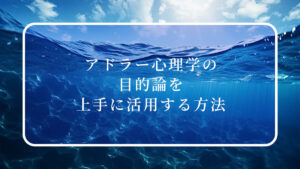
コメント