初対面の人と挨拶して、その場では笑顔で話せたとしても、次に会ったときには「あれ、この人誰だっけ…」と頭が真っ白になります。
仕事でもプライベートでも、「人の顔と名前をしっかり覚える」ことができる人は信頼されやすいし、会話の入り口もスムーズになるのは分かっています。
でも、どうしてもできない。苦手意識だけが積み重なって、余計に混乱する悪循環。
しかし反対に得意な人もいます。
この「顔と名前を覚える能力」って、そもそもどうして人によってこんなに差があるのでしょうか?
得意な人と苦手な人がいる理由を調査してみました。
- 人の顔と名前を覚えられないのはなぜか ─ 記憶がうまく結びつかない理由と心理的な背景がわかります。
- 顔と名前をすぐ覚えられる人の特徴 ─ どんな行動や考え方が記憶を助けているのかが理解できます。
- 名前を忘れないための習慣 ─ 初対面の場面などで実践できる具体的な工夫が学べます。
- 顔と名前が一致しないときの対処法 ─ 気まずさを避ける自然な対応の仕方を知ることができます。
人の顔と名前を覚えられない理由


人の顔と名前を覚えられない原因には、記憶の性質と習慣の両方が関係しているようです。
まず一つ目は、名前が覚えにくい理由に関する指摘:
顔は視覚的な映像情報で、名前は文字情報です。異なる種類の情報をひもづけて覚えることはとても難しく、『人の顔と名前は覚えにくい』と感じる人が多いのはこれが原因です。
映像情報と文字情報は覚えるのが難しいというのはなんとなく理にかなっている気がしますよね。確かに両方を一度に覚えるというのは無理そうです。じゃあどうすればいいの?という話ですが…
初対面の人の顔と名前をしっかり覚えたければ、丸暗記しようとせず、その人のことをよく知り、できるだけ多くの情報を紐づけしながら、印象深く頭に残すようにしてみるとよいでしょう。
これはこれで理解できますが、初対面でそんな多くの情報をまず入手できないケースが多くないですか?と思ってしまいますがどうでしょうね。
記憶は“意識と繰り返し”が鍵であることはわかります。
その前提で覚えられる人と覚えられない人がいるという話なんですが、結局名前を口に出したり、顔の特徴と関連づけてイメージ化したりする姿勢を自分に取り入れるしかないのかもしれません。そして、覚えられる人箱の行動がもしかすると無意識にでもできているのかもしれませんね。
つまり、「覚えるのが苦手」というのは完全に才能のせいではなく、記憶に向ける“意識”と“行動”に差がある可能性がある、ということ。
僕のように、「また忘れたらどうしよう」という不安に引っ張られると、余計に注意力が分散してしまい、覚えること自体がどんどん難しくなっているのかもしれません。
“意識”と“行動”に差があるという点でさらに細分化してみると以下の2点が浮かび上がってきます。
- 相手に興味・関心がない
- 覚える必要性を感じていない
どちらも似ている現象ではありますが、結局のところ「覚えなければいけない状況」において頭では「覚えなければいけない」と思っていても、本心で「覚えなくてもいい」と感じていれば覚えられません。
相手に興味・関心がない
結局これに尽きる部分はあると思います。この場合の多くは、「興味のあるものしか覚えられない」というタイプも多く、相手を知る努力が必要になってきます。
覚える必要性を感じていない
覚える必要性を感じていないというのは、「知らなくてもなんとかなる」パターンや、「自分にとって重要な相手ではない」と感じてしまっているパターンなどがあるかと思います。
この場合は相手に対して失礼なのは重々承知だけどもその都度確認するしかないかもしれませんね。
人の顔と名前を覚えられる理由


反対に人の顔と名前をすぐ覚えられる人はどんな特徴があるのか。またどんなことを意識しているのかを検証します。
観察力が高く、相手の特徴を細かく捉えている
顔の輪郭や髪型だけでなく、仕草や声のトーンなど複数の情報を結びつけることで記憶に残りやすくなります。
名前と情報を関連づけて覚えている
名前を聞いた瞬間に「似た名前の有名人」「響きが近い単語」など、自分の知識と結びつける習慣を持っています。
人への関心や好奇心が強い
相手に興味を持つ気持ちが強いほど、自然に顔や名前を記憶に残そうとする心理が働きます。
繰り返し確認する習慣がある
会話の中で名前を意識的に呼ぶ、心の中で繰り返すなど、小さな習慣が定着につながっています。
ポジティブな感情と結びつけて記憶している
「この人と話して楽しかった」「雰囲気が心地よかった」などの感情が伴うと、顔と名前の記憶が強化されやすいです。
人の名前を忘れないための習慣
名前を聞いたらすぐに繰り返す
初対面のときに名前を聞いても、その場の緊張や話題の切り替えで頭に残らないことがよくあります。そこで有効なのが、聞いた直後に相手の名前を口に出して繰り返す方法です。「〇〇さんはどちらからいらっしゃったんですか?」と会話の中で自然に呼ぶことで、聴覚と発話を通じて記憶に定着させられます。また、心の中で3回唱えるだけでも効果的です。繰り返す行為は単なる記憶術というより、相手に「自分の名前を大切に扱ってくれている」と伝わるという副次的な効果も持っています。
特徴と名前を結びつける
名前は音だけで覚えるより、イメージと組み合わせる方が定着率が高まります。たとえば「田中さん」は「背が高い田中さん」、「鈴木さん」は「穏やかな口調の鈴木さん」といった具合に、外見や雰囲気、話し方の特徴と関連づけると記憶が呼び起こされやすくなります。ビジネスの現場では名刺と顔を同時に眺めて特徴を書き込む人も多いですが、日常会話でも「髪型と名前」「職業と名前」など、何か1つ強く結びつける要素を持っておくと忘れにくくなります。
感情と一緒に記憶する
人は感情を伴った体験を強く記憶に残します。名前を聞いたときに「この人と話すのは楽しい」「なんとなく安心できる」といった感情を意識しておくと、顔と名前が一体となって頭に残ります。逆に印象に残らない会話だと、名前もあっという間に薄れてしまいがちです。意識的に「この人と出会えてうれしい」「また話したい」とポジティブな感情をラベリングしておくことは、単なる記憶術を超えて人間関係を深める基盤にもなります。
繰り返し思い出す習慣を持つ
名前は「聞いた瞬間の努力」だけでなく、その後に思い出す機会をつくることで定着していきます。たとえばその日出会った人の名前を寝る前に振り返る、翌日に会話の中で再び使う、名刺やSNSで顔と名前を確認しておく。こうした小さな繰り返しが、記憶を短期から長期に移行させる手助けとなります。「一度会っただけなのに名前を覚えてくれていた」と言われると、相手との距離も一気に縮まります。つまり習慣化こそが最大のポイントなのです。
顔と名前が一致しないときの気まずさを防ぐ方法
誰しも一度は「顔は覚えているけれど名前が出てこない」「名前は思い出せるけれど顔と結びつかない」といった気まずい瞬間を経験したことがあるはずです。そんな場面をうまく切り抜けるために、日常で実践できるいくつかの工夫があります。
会話の中で自然に名前を引き出す
名前がどうしても思い出せないとき、直接「お名前なんでしたっけ?」と聞くのは角が立つ場合があります。そこで有効なのが、会話の流れの中で相手に名乗ってもらえる状況を作ることです。例えば「名刺をいただけますか?」や「SNSや連絡先でつながりたいです」といった提案をすると、相手は自然に名前を示してくれます。また「漢字はどう書くんですか?」と尋ねるのも、失礼になりにくく名前を確認できる方法です。
第三者を巻き込んで紹介し合う
集まりや会合の場では、周囲の人を活用するのも一つの方法です。知り合いを別の人に紹介する形を取ると、相手が改めて自分の名前を名乗ってくれることがあります。たとえば「こちらは以前ご一緒した方で……」と話し、紹介を促すとスムーズです。この方法は自分が名前を忘れていたことを悟られにくく、同時に場の雰囲気も和やかに保てます。
相手の特徴や会話内容を手がかりにする
どうしても名前が思い出せないときは、まず顔から連想できる特徴や過去の会話内容を思い出してみましょう。「確か旅行の話をした人」「背が高くて眼鏡をかけていた人」など、断片的な情報から記憶をつなげることで名前が浮かぶ場合があります。たとえ名前をその場で思い出せなくても、「以前こういう話をしましたよね」と切り出せば、会話のきっかけになり、気まずさを和らげられます。
正直に伝え、関係を深めるチャンスに変える
場合によっては、無理に取り繕うよりも素直に「すみません、名前がど忘れしてしまって…」と伝える方がかえって好印象になることもあります。誰にでも起こることだと理解されやすいですし、誠実さが伝わることでその後の関係がスムーズになります。特に何度も顔を合わせる相手であれば、ここで無理をするより「正直さ」を選ぶ方が長期的な信頼関係を築くきっかけになります。
まとめ:顔と名前を覚えることが信頼関係につながる
顔と名前を覚えられないという悩みは、突き詰めると脳の構造や記憶力の差、あるいは「病気」や「認知特性」などにも関係してくるかもしれません。
でも、今回の調査を通じて思ったのは、「全てが先天的な問題ではない」ということ。
たとえば「相手の顔を見る意識を高める」「名前をすぐ繰り返す」といった小さな行動だけでも、改善の糸口になる可能性があります。
苦手意識があるからこそ、少しずつ試しながら、自分に合ったやり方を見つけていくのが大事なのかもしれません。
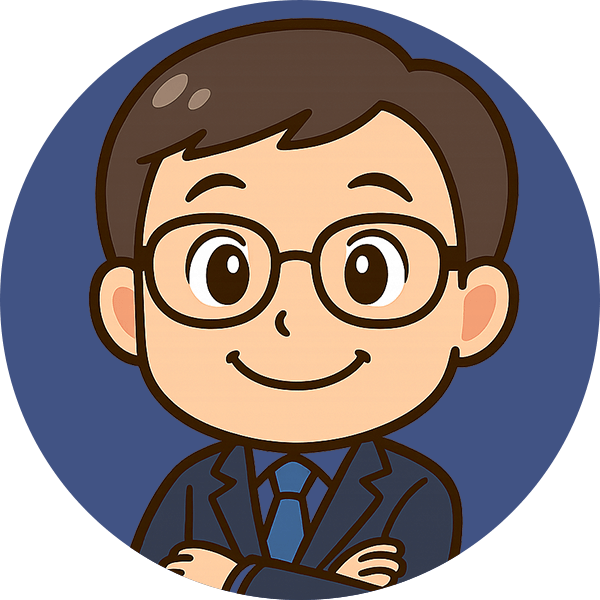

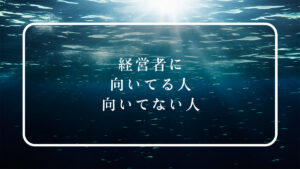
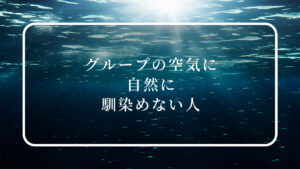
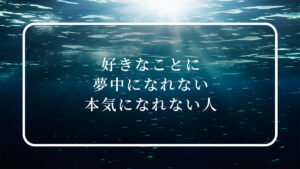
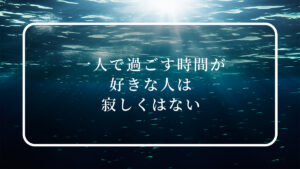
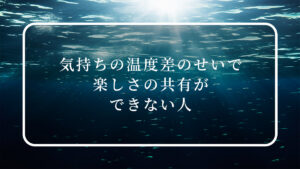
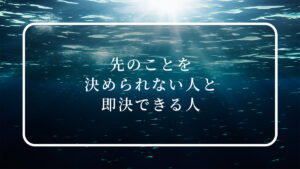
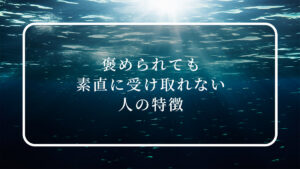
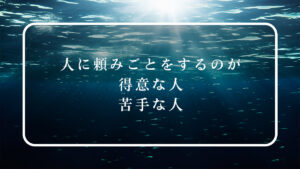
コメント